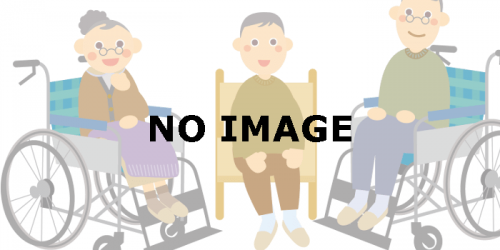
嫌だけどしているはタブー
介護をしていると、尊厳について考えます。
尊厳を守る、尊厳を支えるという意味で使いますが、尊厳とは、「尊くおごそかで侵しがたいこと」です。
個人の尊厳とは、すべての個人が人間として有している人格を、侵せないものとして相互に尊重するという原理を言います。
介護されている方の尊厳と言うと、自分は生きていて良いのだと思えている状態だと言われています。
尊厳を守るイコール、自分の自尊心やプライドをキープできる状態だと私は解釈しています。
親の尊厳を守ること、これは介護をする際にはとても大切です。
「一人で、自立した生活ができる」これこそ、尊厳を守ることができる状態だと思います。
だから、介護では「してあげた」「嫌だけどしている」ということはタブーなんです。
親がしたいことはさしてあげて、危険があったり間違ったことをしていたら、否定をするのではなく正しい方法を発見させてあげる。
言葉で言うのは簡単ですが、実際に実践するのは、中々難しいですよ。
果たして親の尊厳を守れるのか
「○○をして」と言うと、こちらが命令していることとなります。
たとえば、お年寄りの方って、ほとんどのことを「YES」で答えるんですよ。
だから、食事中に「もう食べない?」と聞くと、「うん」と言うんです。
これを、「手伝ったら食べてくれる?」と聞いたら、「うん」と答えて食べてくれるんです。
私たち介護者って、無意識のうちに無理強いしているんですよ。
もう食べないかと聞いて、「もう食べるな」と言っていることと同じ意味になってしまうんです。
尊厳って、こういった気遣いだと思っています。
手伝ったら、してくれるか、そう聞くのが正解なんです。
何事も、無理強いしたらダメなんですよ。
排せつ介助も尊厳を守ることが一番大切
排泄ケアが、一番尊厳を守ることが大切です。
だって、普通は排泄の介助なんて誰も人にしてほしいと思っていませんから。
トイレは自分でできる、これが当たり前です。
5才の子でも、大をした後に自分でおしりを拭きたがりますよ、きっと。
「人にされること」の中で、一番嫌なことだと思います。
尊厳って、イメージはしやすいけど、実際に行動することは大変です。
尊厳を守るにはどうすれば良いのか、まだまだ私のこれからの課題でもあります。
自尊心を高める支援について、これから勉強していきたいです。
親は絶対に、「申し訳ない」って思っているでしょうから。
そう思わせないような介護をしていきたいです。